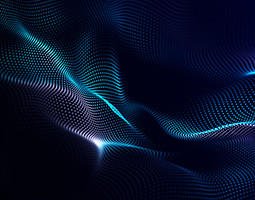保険業界の羅針盤 - 未来の働き方 - 生成AIで描くBX/DXの近未来【第4回】
■調査・分析の軸
消費者のAIに関するスタンスと行動を詳細なレベルで理解するために、四つの主要な柱を中心に分析を行った。
▽購買プロセス:購買プロセスの各段階におけるAIの具体的な利用方法を調査した。すなわち消費者が契約前後にどのように「リサーチ」「意思決定・契約」「保全期間・支払」を行っていくかということであり、保険会社と契約者の関係の核心にあたる。
▽年齢分類:スタンスや行動の違いを把握するために、五つの年齢層に分類した。18~24歳、25~34歳、35~44歳、45~54歳、55歳以上。
▽AIツールの種類:一般的に消費者が利用する可能性のある三つの主要ツールについて、利用嗜好を調査した。音声アシスタント、チャットボット、対話型AI
▽保険商品の種類:一般的な保険商品(生命保険や損害保険)と、投資性の高い保険商品(変額保険や年金保険)という二つの保険商品カテゴリーを分析対象とした。
■各購買プロセスにおけるAI利用動向
リサーチプロセス:保険分野におけるAI導入の最も敷居が低い段階に位置付けられる。
この段階では、保険会社は消費者の興味を引き付け、契約前の意思決定に影響を与える貴重な機会を有している。成功の鍵は、AI利用を促進する要因を理解することにある。すなわち消費者が有用だと感じる点、好むツール、およびAIを活用したリサーチプロセスにおける透明性と信頼性を向上させる方法だ。
年齢分類では、45~54歳の層は、一般的な保険商品と投資性の高い保険商品の両分野でAIを活用する意欲が最も高い。これは定年退職後を見据えた計画などを行うためと考えられる。
最も若い層は、自動車保険の見積もりを比較したり、保険を評価したりするためにAIを活用した比較ツールを利用する傾向が高い。デジタルツールへの依存度が高い世代であることから、AIを活用した保険商品のリサーチは、彼らのデジタル利用の延長線上にあると言える。
AIツールの種類では、対話型AIが好ましい。静的な比較ツールが表面的な価格情報しか提供しないのに対し、対話型AIはアドバイザーとして機能し、消費者が特約、除外事項、パーソナライズされた保険プランの推奨事項を理解することを支援できる。例えば、生命保険を検討中の消費者は、定期保険と終身保険の比較について質問し、長期的な保険料支払いに関するシナリオベースの推奨事項を、複雑な保険書類を閲覧する必要なく得ることができる。このアプローチは、自動車保険や火災保険でも価値がある。これらの分野では、事故歴、地域別のリスク、免責金額などの詳細が保険料に大きく影響するためだ。
保険商品の種類では、投資性の高い保険商品よりも一般的な保険商品の選択肢を調べるためのAI活用が期待されている。この傾向は、比較サイト、保険見積サイトなどの利用が定着していることが背景にあると考えられ、消費者の慣れから来ている可能性が高い。
一方、投資性の高い保険商品はより高い金融リテラシーと信頼を必要とするため、消費者はAIのみに依存してポートフォリオのリサーチを行うことに躊躇(ちゅうちょ)しがちのようだ。
意思決定・契約プロセス:若年層がAI活用をリードするが、相対的に利用への関心は低い。
消費者がAIを自動化に活用する際に重視する点と、最も適したAIツールを理解することが出発点となるであろう。
年齢分類では、35~44歳の層が最も高いAI活用嗜好を示している。この年齢層のライフステージでは、消費者は長期保険の加入、高価値な投資の管理、さまざまな家計上の支出など、新たな取り組みを始める時期にあたる。これらが、AIツールを利用した契約プロセスの簡素化・自動化に対する期待を高めている可能性が高い。
最も若い消費者層(18~24歳)は保険契約におけるAI活用に中程度の関心を示している。これは、自動車保険の需要が主な要因と考えられる。自動車保険は、多くの人々が最初に接する主要な保険商品であるためだ。また、若年層は投資性の高い保険商品により慎重な姿勢を示しており、これは低い金融リテラシーとリスク感度が関連している可能性が高い。
55歳以上の層は、特に投資性の高い保険商品では伝統的な意思決定手法への依存が続いている。AIは保険契約の最適化や投資調整において役割を拡大しているが、この世代における信頼を獲得しているとは言い難い。
保険商品では、一般的な保険商品が投資性の高い保険商品よりもAI利用が優位となっている。リサーチ段階と似ているが、投資性の高い保険商品には高い金融リテラシーと信頼が必要だが、一方で一般の保険商品の購入は構造化されており、標準化された引受原則、定義された保障階層、規制上の保護措置が確保されている。一般の保険商品の中でも、生命保険は長期的な財務的影響を伴うため、より慎重な利用曲線を描くであろう。AIはニーズ分析、シミュレーション、引受審査を支援できるが、消費者は財務の安全性が透明性と公平性に基づいて評価されていることを確認したいと考え、AI単独による判断を避ける傾向がしばらく続くだろう。
AIツールの種類では、対話型AIが引き続き主要な選択肢だが、その役割はリサーチ段階とは異なる。意思決定・契約段階では、対話型AIは用語の明確化、特約等の選択肢などの消費者の意思決定支援に利用されるであろう。ただし、契約の完全自動化は依然として限定的で、特に投資性の高い保険商品では信頼と規制遵守の要件から、ハイブリッドアプローチが求められている。
保全期間・支払のプロセス:AI利用への関心は低いものの、大きな機会が存在する。
このプロセスでは、AI利用に対する最も大きなためらいが見られる。購買プロセス全体で最も低く、特に技術への快適性に関する要素が最も低くなっている。これは、保険商品に関するやり取りする際、各保険会社が提供するスマートフォンアプリなどのエクスペリエンスが成熟していないことや、デジタル技術を使用する意欲の欠如が現れていると考えられる。
このプロセスでのAI利用への関心の低下は、当社の業界横断レポートで示された傾向と逆行している。一般的には、商品購入後の保守の段階では購入段階に比べてAI利用への関心が上昇する傾向が見られる。また、AI技術が保険商品やサービスとの購入後のやり取りを大幅に簡素化できるという保険会社側の期待とも矛盾している。例えば、リアルタイムの保険契約更新情報の提供、個人に合わせたリスク管理の支援、カスタマーサポートの効率化、または顧客のニーズの変化に応じて保険契約の調整を通知する能動的なアラートを提供するなどだ。
逆に言うとこのプロセスでは、利便性の向上と能動的なサポートを通じて、保険会社と契約者の関係を厚くし、拡大するというAIの大きな可能性があると言える。
AIツールの種類では、シンプルな手続やアクションは静的なチャットボットが、問合せやさまざまなインサイトの取得には対話型AIが好まれる傾向があるようだ。
これは、契約情報の変更や保険金の請求などは事前に定義され構造化されたプロトコルに従うのに対し、問合せや投資インサイトなどは最終的な情報を得るために会話を重ねる必要があるからだと考えられる。
一方で契約者が契約期間を通じて保険会社から支援されていると感じるのは、やはり対話型AIが有利であり、この二つのツールは一つに進化していくだろう。
■消費者のニーズに応える
消費者のAI利用は急速に拡大しており、それに伴い消費者向けAIエージェントの受け入れも進んでいる。保険消費者にとって、AIエージェントは個人向けのリスクマネージャーや保険アドバイザーとして機能し、請求の追跡、保険内容の最適化、最適な保険プランの確保など、複雑なタスクを調整する役割を果たすであろう。間もなく、私たちが知るインターネットは「エージェント型インターネット」へと進化する。これは、AIを活用したツールやエージェントが相互接続されたエコシステムであり、人々が依存する製品やサービスを〝自律的に〟検索、評価、購入、維持する仕組みとなる。
保険業界にとってこのことは、これまで以上にさまざまな金融・保険エコシステム内の他のサービスプロバイダーと深く連携しなければいけないことを意味する。例えば、支払いサービスプロバイダー、フィンテックイノベーター、医療やスマートホーム技術、またウェルビーイングを含む健康維持を生業とする業界などが考えられる。
以下のような点を考慮に入れると良いだろう。
- 消費者は、AI等を利用した保険プロセスの完全自動化に躊躇しており、特に投資性の高い保険商品や請求処理のようなセンシティブな領域における「利用段階」でその傾向が顕著となっている。AIによる分析と人間の介在を組み合わせたハイブリッドアプローチが有効と考えられる。すなわち、初期の推奨事項の生成、リスク評価、また定型的手続を効率的に進める、などにAIを、一方で複雑な洞察の解釈、消費者が必要とする共感と安心感の提供においては人間の介在を、という分け方となる。
- 対話型AIを活用してリサーチプロセスを最適化する。これは、保険会社が早期に消費者と関わり、信頼の基盤を築く絶好の機会となる。保険会社は、保険商品のリサーチ、比較、複雑な用語の理解を支援するパーソナライズされたエクスペリエンスを提供するため、対話型AIに注力した方が良い。
- 保険のバリューチェーン全体を通して、年齢層ごとに機能・エクスペリエンスを優先した戦略を再構築する必要がある。上述したように調査結果から、保険の購買プロセスにおける年齢ごとの消費者エンゲージメントに明確な差異があることが判明した。全ての年齢層の実際のニーズに焦点を当てる必要がある。
■おわりに
AIを取り込んでいく世界は、消費者側でも保険会社側でも始まっているが、AIテクノロジーの行き着く先を含めて最終形はまだ見えていない。しかしながらおぼろげな形は見え始めているのは明らかだ。保険会社は生き残りをかけて〝今〟知識と経験を蓄積する必要があるのではないだろうか。