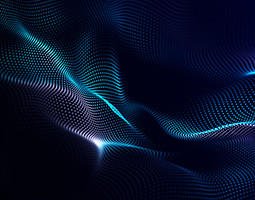保険業界の羅針盤 - 未来の働き方 - 保険業界におけるオフショア戦略の転換トレンド
現在、日本の金融・保険業界ではオフショア拠点の見直し機運が高まっている。これまで中国・大連がBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)、ITO(ITアウトソーシング)の中心地だったが、地政学リスク/カントリーリスク(以下、地政学リスクとする)の高まりや人件費の上昇を受け、大連以外、あるいは大連+1を模索する動きが始まっている。本記事では、日本の保険業界がオフショア拠点をどのように見直しているのか、その背景や新たな候補地、そして今後の見通しについて詳しく解説する。
なぜ「大連」だったのか?―保険業界のオフショア拠点の歴史
■大連が選ばれた理由
中国・大連は、これまで日本の保険業界にとってオフショア業務の中心地だった。特に、コールセンター、データ入力、保険契約のバックオフィス業務などのBPO、アプリケーション開発でのコーディング業務などのITOが盛んに行われてきた。大連が選ばれた背景には、以下のような要因がある。
- 日本語人材の豊富さ
大連は日本との関係が深く、多くの大学で日本語教育が行われている。日本語を話せる人材が比較的安価で確保できるため、保険業務に適していた。 - コストの優位性
日本国内での人件費と比べて、圧倒的に安価に業務を遂行できた。特に、2000年代以降は円高の影響もあり、コスト面でのメリットが大きかった。 - BPO/ITOの基盤が整っている
大連には多くのIT企業が進出しており、オフショア業務のインフラが整っていた。日本企業が集中することで、日本向けの業務に特化したサービスが充実していた。こうした理由から、日本の保険業界は大連を中心にオフショア業務を展開してきた。
なぜ今「大連」以外が求められるのか
1. 中国との地政学リスクの高まり
経済安全保障、地政学リスクなどの言葉がメディアで口にされるようになってきた。大まかに言えば「経済安全保障」とは国家の安全保障を経済的な側面から確保するコンセプトだ。一方で「地政学リスク」とは経済安全保障を確保するにあたって考慮しなければならない地域や国によるリスクを指す。
日本では「経済安全保障推進法」が2022年に成立・交付されたが、この法律の下で創設された四つの制度のうち、主に「基幹インフラ役務の安定的な提供の確保に関する制度」の中で「特定社会基盤事業―金融に関わる事業」として保険業が指定されている。つまり、保険会社は経済安全保障を考慮して経営計画を策定する必要があるということだ。
近年、米中関係の悪化や台湾有事の懸念など、地政学的なリスクが高まっていたが、トランプ大統領の2期目就任に伴い、世界の状況は一気に不透明化し、こういったリスクがリスクで済まない可能性も大きくなってきている。
日本と中国の関係が悪化しないまでも、もしアメリカと中国の関係が悪化した場合、日本も影響を受けることは火を見るよりも明らかだ。
▽BPO/ITO拠点の業務が停止する可能性▽データセキュリティー上のリスクの増大―といった問題が発生する恐れがある。特に、保険業界は顧客の個人情報を扱うため、情報管理の厳格化が求められる。中国政府の規制が強化される中で、データの取り扱いに慎重になる企業が増えている。
2. 人件費の上昇
中国の経済発展とともに、人件費も大幅に上昇している。過去には日本の10分の1以下だった人件費が、現在では一部の都市では日本と大差がなくなってきている。
このため、「コスト削減」という目的でのオフショアが難しくなりつつある。特に、より安価な人材を求める企業は、東南アジアなどの他の地域への移転を検討するようになった。
また、企業によってはオフショアから撤退し、国内回帰を進めていたところもあるが、インフレの進行とそれに伴う給与の上昇により、日本でも人件費が上がり始めたため、再度他の地域への移転を検討する企業でも出てきた。
3. 日本の人口減少と労働力不足
人口減少とそれに伴う労働力不足は、現在の経済活動にとってすでに大きな課題だが、解消されるどころか進行することが見通せていることから、今後の経済活動にとっても非常に大きな課題といえる。
参考までに、日本の人口減少と労働力不足の現状を、数字を交えて以下に挙げておく。
▽総人口の減少:2023年には約1億2400万人→2040年予測は約1億1000万人→2060年予測は約8700万人。
▽生産年齢人口(15~64歳)の減少:1995年には約8700万人→2023年には約7400万人→2040年予測は約6200万人→2060年予測は約4500万人に半減。
▽地方の過疎化:東京一極集中が続く一方で、地方では人口流出が加速し、労働力不足が深刻化。
以下のように労働力不足への対策も実施されているが、決定打となるものがないのは共通認識といえる。
▽外国人労働者の受け入れ拡大
▽女性・高齢者の活躍推進
▽生産性向上(DX・自動化)
▽働き方改革
こういった状況を鑑みて、企業は対策を進める必要があるが、その一つが多拠点化を考慮したオフショア活用といえる。これまで大連のみをオフショア拠点として利用してきた企業だけではなく、オフショア拠点を利用してこなかった企業も、業務を分散し、リスクを低減する「多拠点化オフショア戦略」が求められている。
多拠点化オフショア戦略の有力候補地
金融・保険業界が「多拠点化オフショア戦略」の候補地として注目しているオフショア拠点には、以下の国々がある。それぞれ特徴も付記した。
〈インド(バンガロール、プネ、チェンナイ等)〉
▽人口約14億人+▽言わずと知れた英語圏では古くから実績のあるオフショア拠点▽英語圏ではBPO、ITOともに実績があるが、日本では主にITOオフショア拠点として利用(日本向けのBPOはまだ少ないが、今後の発展が期待される)▽英語対応が基本となるため、日本語対応には課題があったが、最近ではインド各地の大学で日本語を学ぶことができるようになってきた▽ITO全般、データ分野に強みがある。英語圏の実績があるため、新規技術や最先端プロジェクト経験者など、多様な人材の確保は他国の追随を許さない
〈マレーシア(クアラルンプール、ペナン)〉
▽人口約3400万人▽クアラルンプールは、規模は小さいが日本でも古くから実績があるオフショア拠点▽多民族国家であり、英語・日本語対応の人材が確保しやすく、日本文化への親和性も高い。また、日本に留学していた関係で文化にもある程度適応している人材もいる
〈フィリピン(マニラ、セブ)〉
▽人口約1億人+▽英語が公用語であり、グローバル対応が可能▽BPO(コールセンター、バックオフィス)の実績が豊富▽コストが安価であり、拡張性が高い
〈ベトナム(ホーチミン、ハノイ)〉
▽人口約1億人▽一番新しい日本向けの主要オフショア拠点▽日本語を学ぶ若者が多く、日本企業の進出も活発▽IT人材の育成が進んでおり、BPOとの相性も良い▽政治的に安定しており、親日的な国民性
多拠点化オフショア戦略推進への今後の展望
大連以外のオフショアを考慮するにあたり、考慮すべきポイントがいくつかあるのでそれを紹介する。
まず大前提として、これまでの大連へのオフショアは、主にBPO、ITOとも日本で仕様を決めて、オフショア側ではそれらを忠実に実行する形をとってきた。BPOとしては業務手順を日本側で定義し、大連で実施するという流れだ。ITOでいえば要件定義、設計は日本でやりきって、コーディング、ユニットテストはオフショアで実行し、その後日本に戻すという流れだ。
しかしながら、今後は日本で仕様を決めるその人材さえ不足してくると思われる。これは各社で同様のタスクを今実施している社員がシニアなメンバーであり、すでに定年退職も視野に入っているであろうことから容易に想像できる。つまり、今のうちにそういった部分もカバーできるように何らかの施策を実施する必要がある。
次に、上記からのつながりでもあるのだが、企業によっては、「自社の業務をキレイにしてからオフショア化しよう」というケースが見受けられることだ。例えば業務自動化もその一つといえる。デジタル化/自動化の強化を進めて、例えば生成AIやRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を活用し、業務そのものを低減しようという考え方だ。この考え方自体は何も間違っていないが、こういった施策を行う際は検討や実装そのものにオフショアを活用すべきだ。特にインドのオフショアは欧米のプロジェクトを多数実施しているため、経験豊富な人材が多い。一部業務のみをデジタル化/自動化するのではなく、オフショア化を行い、業務を移転した上で自動化目標を設定し、一連の業務を全てデジタル化/自動化する形で進めるという考え方もある。
オフショアを決定する際の優先順位の付け方も要注意だ。大連と同じように「日本語」を第1優先にしてしまうと、本質を見失う可能性が高い。自社が何を求めてオフショア化するのか、改めて目的を考える必要がある。何をどのようにオフショア化したいのかを、今後3~5年を見据え議論する必要性がある。
おわりに
前述してきたように、オフショアを利用しないという戦略をとってきた企業も含めて、日本の保険業界はオフショア戦略の見直しをするべき時期に来ている。「大連一極集中」から「多拠点化オフショア戦略」へと移行する時代では、地政学リスクや人件費の上昇を考慮しつつ、どの国・地域に拠点を置くかを選ぶ必要がある。
特に、上述した国々が「ポスト大連」として有力視されるが、それぞれの国の強みを生かしながら、最適なオフショア戦略を構築することが求められている。
今年に入って当社も説明や視察のお問合せを頂いているが、すでに昨年の件数を超えている。私自身も今月お客さまをインドにご案内したばかりだ。保険業界がどのような形でオフショア業務を進化させていくのか、引き続き注視していく所存だ。