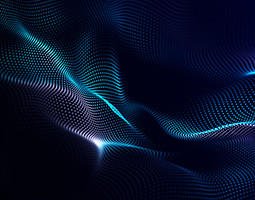保険業界の羅針盤 - 未来の働き方 - 保険会社が持続可能性社会の進展で中心的役割を果たすために
「脱炭素」「カーボンニュートラル/オフセット」「ゼロ・エミッション」「再生可能エネルギー」、そして「持続可能性」。一般的には、持続可能性を向上させるという点で、保険業界は最もインパクトの小さい業界の一つに思われているかもしれない。保険会社は炭素集約型の製造工場を持っているわけでもなく、貴重な天然資源を集中的に使用しているわけでもなく、排出量を分析し削減する必要のある複雑なサプライチェーンを必要としているわけでもない。しかし、保険業界こそは自身の事業の持続可能性の向上だけではなく、社会全体の持続可能性の推進へも大きな貢献ができるほとんど唯一の業界ではないだろうか。
持続可能性ビジネスへの展望
さまざまな業界で関連した取り組みが行われているが、保険業界でも持続可能性をビジネスの成長に結び付けようとしている。しかしながら、昨年のネットゼロ保険同盟(NZIA)からの脱退騒動(米国での事業継続や訴訟のリスクを勘案したものと考えられている)や、ロシアのウクライナ侵攻を受けてドイツが石炭火力発電の再稼働を決定したことなど、予期せぬ政治的出来事が持続可能性の進捗にマイナスの影響を与えている。
一方で、世界の保険会社は持続可能性ビジネスが将来の成長戦略の大きな部分を占めるようになると考えているようだ。持続可能性への取り組みが自社の業績に与える影響は、現時点では「中立」もしくは「ややマイナス」と考えていても、時間の経過とともに、2030年までには80%の保険会社が「プラス」または「非常にプラス」に働くと考えているとの調査結果もある。
社会的な不確定要素はあるにせよ、保険会社はコントロールできる範囲の根本的な課題を克服することで、持続可能で成功しやすいビジネスへとシフトすることができるのではないだろうか。また、保険会社の特徴である引受と投資という両輪を利用することで、社会の持続可能性を推進させることができるのではないだろうか。
保険商品・保険ソリューションへの考察
潜在的な損失を軽減しつつ、増大するリスクをカバーする商品やソリューションを開発することは、保険業界にとって一義的に不可欠である。
化石燃料を利用した発電所と比較して、再生可能エネルギーを利用した発電所は、その性質上、耐用年数の間、常にさまざまに変化するリスクに直面する。設置される場所の関係で建設中のサプライチェーンは相対的に難易度が高く、開発の初期段階におけるエンジニアリングの問題や、稼働した後の運用リスクなどが考えられる。実際、気候変動の影響で自然災害を受けやすい場所に設置されることが多いため、風力発電と太陽光発電の両方で損失が拡大している。過去10年間、保険会社は風力発電所の物的損害や収入減に関連して多額の保険金を支払っており、そのうちのいくつかは保険料の支払額を上回る保険金だった。
自然災害に関するリスクはますます複雑化し、予測不可能なものとなっているため、保険業界がリスクを相殺する方法の一つとして、より信頼性が高く、費用対効果の高い補償を提供するパラメトリック保険を利用するようになっている。パラメトリック保険は、実際に発生した損失を補償する代わりに、あらかじめ定義された事象が発生する確率をカバーするもので、再生可能エネルギー事業を財政的に実行可能なものにすると同時に、保険会社にとっては保険金支払いを予測できるため、リスクは相対的に低い。
パラメトリック・ソリューションへの需要はすでに高まっている。Swiss Reによると、世界のパラメトリック保険産業は21年に117億米ドルを生み出し、31年には293億米ドルに増加する可能性がある。このソリューションは、保険業界が直面する最も重要な問題の一つである支払いまでの「対応時間」も解決する。パラメトリック保険は、反応時間を数カ月から数日、場合によっては数時間にまで短縮する。
大手保険会社がこの分野で増強を図っているのは驚くことではない。例えば、仏AXAグループは、天候、気候、パラメトリック・リスク移転の専門部門であるアクサ・クライメイトを立ち上げた。また、最近、サイクロンのパラメトリック・リスク移転をより迅速かつ正確にすることを目標に、災害モデリング、気候分析、データのスペシャリストであるReaskとの新たな提携を発表した。
日本でも大手損保3社からパラメトリック保険商品が提供されており、今後企業や団体だけではなく、個人の保険商品に対しても拡大が期待されている。
引受と投資への考察
保険会社には、化石燃料事業への引受と投資という、長く継続的な歴史がある。最近の調査によると、保険会社はいまだに化石燃料事業に5兆円以上を投資している。しかも、石油・天然ガス事業への引受や投資の制限を行う保険会社の数の伸びは、近年鈍化している。過半数を超える保険会社が、自社の事業戦略において持続可能性の重要性が「高い」、あるいは「非常に高い」と回答しているにも関わらずである。
保険会社にとって持続可能性が戦略的優先事項である理由は明らかだ。気候変動問題が深刻化する中、気候変動の影響が疑われる災害に対する保険金の支払額は、過去10年間で倍増したとの試算もある。Swiss Reによれば、自然災害による世界の経済損失は22年には2750億ドルに達し、保険会社はその45%にあたる1250億ドルを負担することになった。経済的視点で見ると、23年上半期までに自然災害による世界の経済損失はすでに1940億ドルに達しているという。
一部の保険会社はこの問題に直接対処するための行動をとっている。例えば米Chubb保険は、石油・天然ガス事業の引受基準として、顧客にメタン排出量の削減を義務付ける制約を課し、また、政府が保護する自然保護地域での石油・天然ガス事業へ保険を提供しないことを発表している。
投資に関しても同様だ。再生可能エネルギーは新分野の事業のため、化石燃料事業と比較して投資リスクは相対的に高いと言えよう。しかしながら、保険事業の公共性を考えるとき、投資先の緩やかなシフトは避けて通れない道であろう。
次のステップに進むための考察
■専門性の課題
保険会社がポートフォリオ全体に持続可能性要素を取り入れようとするとき、多くの課題に直面する。われわれの調査では、戦略的な整合性と明確性の欠如が最大の課題として挙げられている。
その要因の一つは、専門知識の不足である。例えば、化石燃料事業にサービスを提供してきた長い歴史を持つ保険会社は、保険設計の仕様や統計記録に関しては経験が豊富であるが、再生可能エネルギー事業が内包するリスクに関しては経験が乏しい。
専門知識の問題を解決するために、保険会社の94%が従業員のスキルアップを計画しており、83%がそのギャップをパートナーシップで埋めることを計画している。
例えばパートナーシップでは、マネージング・ゼネラル・エージェント(MGA)などは貴重なパートナー候補である。MGAは、保険会社に代わって保険引受を行う権限を持つ専門の保険代理店である。パートナーシップを通じて、保険会社は新しい社内インフラに投資することなく、新しい市場に参入することができる。特定のMGAは、気候変動に関連する新たな保険種目について、引受の高度化や経験を提供することができる。
気候変動に特化したMGAである英Skyline Partnersとパートナーシップを組んだMunich Reや、MGAのフロンティング会社である米Transverseを買収したMS&ADなどが挙げられる。この傾向は、企業向け気候サービスの機会の大きさと規模がより広く理解されるにつれて、さらに続くだろう。
■技術革新がもたらすリスク評価の課題
激しい競争により、再生可能エネルギーメーカーが提供する技術、材料、製造方法は急速に進歩している。しかし、この事業が比較的新しいものであることは、保険を掛ける上で不利に働くこともある。というのも、保険会社がこれらの技術の実用性や耐用年数、ひいては残余リスクやリスクを公正に評価できるのは、「約8000時間規模で」「さまざまな環境で」使用された後だからである。
特に再生可能エネルギー設備の規模と技術の複雑さが増しているため、修理費用の補償も問題である。再生エネルギーに特化した保険会社である米GCube Insurance(20年に東京海上ホールディングスが買収)の報告書によると、頻繁に設置されている8メガワットの巨大なタービンは、部品の故障が発生しやすい。同報告書によると、8メガワット以上のタービンは運転開始後2年間で部品の故障に見舞われ、タービン保険金請求の55%を占めている。新しい技術には一貫した技術評価と引受の専門知識が必要であり、リスクコンサルタントやエンジニア、ひいては保険引受人にとって、国際的な技術基準や認証を常に最新に保つことは、技術の進歩とともにますます難しくなっている。
プラス面ももちろん存在する。例えば、より頻繁な遠隔評価を支援するテクノロジーが注目を浴びている。世界的な専門保険会社である英Tokio Marine Kiln(08年に東京海上ホールディングスが買収)は、山火事やハリケーンなどの大規模な自然災害が発生した際、査定人が物理的にこれらの地域にアクセスできない場合に、ドローンを使用して損害査定を行っている。こういった損害査定は、保険会社の目的だけではなく保険会社が支援する事業会社の目的にも利用できる。さまざまな事業の早期回復を狙い、交換部品の必要性を先取りしたり、サプライチェーンの寸断の回避にも役立つことは明白だ。
おわりに
これまで述べてきた通り、保険商品・ソリューション、引受と投資先、パートナーシップ、テクノロジーなど、できることはまだまだあることが理解していただけたであろうか。このように、保険会社が持続可能性戦略を策定する際に検討すべき分野がいくつかあることは明らかである。こういった機会を捉えることで、保険会社が自身の持続可能な事業運営による利益を確保すると同時に、保険業界は社会における持続可能性推進の中心的役割を担うことができるであろう。